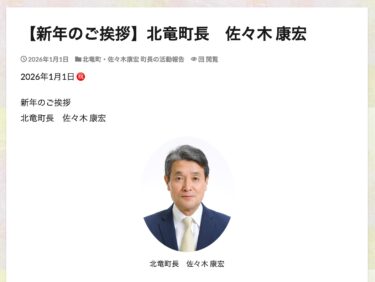วันอังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2568
- 1 พันธะผูกพันที่หล่อหลอมด้วยดอกทานตะวัน มหาวิทยาลัยราคุโนะ กักคุเอ็น และเมืองโฮคุริว ลงนามข้อตกลงความร่วมมือที่ครอบคลุม เพื่อร่วมกันสร้างอนาคต!
- 2 ภาพถ่ายอื่นๆ
- 3 บทความที่เกี่ยวข้อง
พันธะผูกพันที่หล่อหลอมด้วยดอกทานตะวัน มหาวิทยาลัยราคุโนะ กักคุเอ็น และเมืองโฮคุริว ลงนามข้อตกลงความร่วมมือที่ครอบคลุม เพื่อร่วมกันสร้างอนาคต!
เมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราคุโนะ กักคุเอ็น และเมืองโฮคุริว ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือฉบับสมบูรณ์ ณ ศูนย์สุขภาพศาลาว่าการโฮคุริว ความสัมพันธ์อันยาวนานที่ฮิมาวาริได้สร้างขึ้นนี้ จะเป็นก้าวสำคัญในการเปิดอนาคตของภูมิภาคและมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ของข้อตกลงและโครงการความร่วมมือ
ข้อตกลงความร่วมมือที่ครอบคลุมนี้มุ่งหวังที่จะเสริมสร้างการวิจัยทางวิชาการและยกระดับการศึกษา ด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล สติปัญญา และทรัพยากรวัตถุของแต่ละฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราคุโนะ กักคุเอ็น และเมืองโฮคุริว ข้อตกลงนี้ยังมุ่งหวังที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอุตสาหกรรมในท้องถิ่น การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน การฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น และการพัฒนาสวัสดิภาพของประชาชน
เสาหลักสี่ประการของความร่วมมือ
- เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
- เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การวิจัย และการสำรวจ
- การใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่มีอยู่เพื่อการทำงานร่วมกัน
- เรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับความร่วมมือ
ภาพบรรยากาศพิธีลงนาม
แนะนำผู้เข้าร่วม
งานนี้ดำเนินรายการโดย Yayoi Kawamoto จากฝ่ายกลยุทธ์อนาคตของเมือง
แนะนำผู้เข้าร่วมงาน
- มหาวิทยาลัยราคุโนะกาคุเอ็น
ถึงทุกคนในมหาวิทยาลัยราคุโนะกาคุเอ็น - ประธานาธิบดีฮิเดโตโม อิวาโนะ
- นายเคนทาโร โคอิโตะ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ อาหาร และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- ศาสตราจารย์ชิเงรุ อาเบะ ภาควิชาวิทยาศาสตร์อาหารและสุขภาพ วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์อาหารและสิ่งแวดล้อม
- เมืองโฮคุริว
- นายกเทศมนตรียาสุฮิโระ ซาซากิ
- รองนายกเทศมนตรี มาซาอากิ โอคุดะ
- โยชิกิ ทานากะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา
ภาพรวมของข้อตกลง
เรียวตะ ฮาชิโมโตะ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์อนาคตของเมือง อธิบายประวัติและวัตถุประสงค์ของข้อตกลง
ในเมืองโฮคุริว การผลิตน้ำมันดอกทานตะวันหยุดลงในปี 2546 ดังนั้น โครงการฟื้นฟูน้ำมันดอกทานตะวันจึงได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี 2558 ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ด้วยความช่วยเหลือของศาสตราจารย์ชิเงรุ อาเบะ จากมหาวิทยาลัยราคุโนะงาคุเอ็น เราได้ทำงานเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมในท้องถิ่นโดยการปรับปรุงคุณภาพของน้ำมันดอกทานตะวัน
“ผ่านความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา เรามุ่งหวังที่จะใช้ทรัพยากรของแต่ละฝ่ายร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกัน ขยายการวิจัยทางวิชาการและยกระดับการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมอุตสาหกรรมในท้องถิ่น มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และมีส่วนสนับสนุนในการฟื้นฟูชุมชนในท้องถิ่นและปรับปรุงสวัสดิการของผู้อยู่อาศัย” หัวหน้าฝ่ายฮาชิโมโตะอธิบาย
การลงนามสัญญา
ประธานาธิบดีอิวาโนะและนายกเทศมนตรีซาซากิลงนามข้อตกลงและจับมือกันอย่างแน่นหนา
การถ่ายภาพ
ความคิดสำหรับอนาคต: สวัสดี
นายกเทศมนตรีเมืองโฮคุริว นายยาสุฮิโระ ซาซากิ
"ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับข้อตกลงความร่วมมือที่ครอบคลุมในวันนี้ พิธีลงนามในวันนี้เป็นสิ่งที่เรารอคอยมานาน ทางเมืองได้เฝ้าติดตามศาสตราจารย์อาเบะอย่างใกล้ชิดในขณะที่ท่านกำลังทำการวิจัย ผมได้เห็นนักเรียนทำงานหนักด้วยตัวเอง และชาวเมืองก็เช่นกัน เมื่อเห็นความสัมพันธ์นี้ ชาวเมืองจึงรู้สึกว่านี่คือโรงเรียนโคนมที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง
ฉันได้ปรึกษากับศาสตราจารย์อาเบะถึงวิธีที่เราจะสามารถดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปได้ และฉันมีความสุขและขอบคุณจริงๆ ที่เราสามารถไปถึงจุดนี้ได้ในวันนี้
วันนี้เราได้ลงนามในข้อตกลงกันแล้ว แต่ผมเชื่อว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ดังนั้นผมจึงอยากขอให้เรารักษาความสัมพันธ์กันให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ถึงแม้จะเริ่มต้นจากน้ำมันดอกทานตะวัน แต่ฉันได้ยินมาว่าที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมทั้งด้านอาหาร เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม และเกษตรอัจฉริยะ หวังว่าคุณจะทำให้โฮคุริวเป็น "เมืองที่คุณสามารถทดลอง" สิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ ขอบคุณมาก
เราได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทุนฟื้นฟูภูมิภาค 2.0 และได้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ชื่อว่า 'ฝ่ายกลยุทธ์อนาคตของเมือง' และเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่นี้ เมืองโฮคุริวกำลังมองไปสู่อนาคต ด้วยการสนับสนุนจากทุกคนในราคุโนะ กาคุเอ็น และด้วยความหวังที่จะทำงานร่วมกันเพื่อโฮคุริว โซราจิ ฮอกไกโด และญี่ปุ่น เราจึงต้องการสร้างสรรค์เนื้อหาความร่วมมือที่ครอบคลุมของเรา ขอบคุณมากที่มาร่วมงานในวันนี้" นายกเทศมนตรีซาซากิกล่าว
นายฮิเดโตโม อิวาโนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราคุโนะ กาคุเอ็น
ผมขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อทุกคนที่ช่วยให้เรามาถึงจุดนี้ และต่อพิธีลงนามข้อตกลงที่เราจัดขึ้นในวันนี้ ผมตั้งตารอที่จะเริ่มต้นใหม่จากที่นี่
มหาวิทยาลัย Rakuno Gakuen ดำเนินกิจการเป็นมหาวิทยาลัยที่ปลูกฝังทรัพยากรมนุษย์ให้มีสุขภาพดีจากเกษตรกรรมและดิน โดยมีรากฐานจากจิตวิญญาณผู้ก่อตั้งที่ว่า "แผ่นดินสุขภาพดี ผู้คนสุขภาพดี"
ด้วยจำนวนประชากรวัย 18 ปี ที่ลดลงเมื่อเร็วๆ นี้ ทำให้เกิดคำถามว่ามหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่างๆ ควรอยู่รอดได้อย่างไร ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยมากกว่า 800 แห่งทั่วประเทศ และด้วยจำนวนประชากรที่คาดว่าจะลดลงอีกตั้งแต่ปี 2030 เป็นต้นไป การคาดการณ์บางส่วนชี้ให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยเหล่านี้กว่า 200 แห่งจะถูกบังคับให้ปิดตัวลง
ในทางกลับกัน ฮอกไกโดสนับสนุนการเกษตรกรรมให้กับทั้งประเทศญี่ปุ่น โดยมีอัตราการพึ่งพาตนเองสูงกว่าปี 200% อย่างไรก็ตาม จำนวนประชากรและเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม กำลังลดลง รวมถึงในฮอกไกโดด้วย
ในบริบทนี้ เรากำลังหารือกันภายในมหาวิทยาลัยว่ามหาวิทยาลัย Rakuno Gakuen ควรเป็นอย่างไร และจะเปิดตัวแผนกใหม่ในปี 2569 เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรมรูปแบบใหม่ นั่นก็คือเกษตรกรรมอัจฉริยะ
ผมเชื่อว่ามหาวิทยาลัยราคุโนะ กะคุเอ็น มีหน้าที่ "จัดหาทรัพยากรมนุษย์ที่สนับสนุนท้องถิ่น" หากสังคมมีโครงสร้างแบบพีระมิด แม้ว่าจะมีคนเก่งๆ เพียงไม่กี่คนบริหารสูงสุด สังคมก็จะล่มสลายหากปราศจากคนกลางและคนชั้นกลาง สิ่งเหล่านี้คือ "ทรัพยากรมนุษย์ที่สนับสนุนภูมิภาค" และมหาวิทยาลัยราคุโนะ กะคุเอ็น จำเป็นต้องปลูกฝังทรัพยากรมนุษย์เหล่านี้ ผมใคร่ครวญถึงเรื่องนี้และตระหนักว่านี่คือเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งของเรา
ท่ามกลางสถานการณ์ทั้งหมดนี้ ความสัมพันธ์ผ่านน้ำมันดอกทานตะวันได้นำไปสู่ความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างมหาวิทยาลัยและเมืองโฮคุริว ทางมหาวิทยาลัยมองว่าความร่วมมือนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด เราหวังที่จะไม่เพียงแต่ทำงานด้านดอกทานตะวันเท่านั้น แต่ยังมุ่งแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น พานักศึกษาของเราไปกับเรา และร่วมมือกับเมืองโฮคุริวเพื่อสนับสนุนฮอกไกโดและญี่ปุ่น เราหวังที่จะใช้ความสัมพันธ์อันยอดเยี่ยมนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาความสัมพันธ์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานกับท่านในอนาคต" อธิการบดีอิวาคุระกล่าวในพิธีเปิด
ถาม-ตอบ: ความร่วมมือที่เฉพาะเจาะจงและแนวโน้มในอนาคต
1. ความท้าทายในอนาคต
เมืองโฮคุริว: การสร้างแบรนด์ดอกทานตะวันและการทำลายนกและสัตว์
- นายกเทศมนตรีซาซากิ:จนถึงปัจจุบัน เรามักถูกถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างชื่อแบรนด์ 'ฮิมาวาริ' กับผลิตภัณฑ์จริงอยู่เสมอ การนำกากน้ำมันดอกทานตะวันมาทำเป็นปุ๋ย แล้วใช้ปุ๋ยนั้นปลูกข้าว แตงโม และแตงโม จะทำให้ผลิตภัณฑ์พิเศษทั้งหมดของเมืองนี้เชื่อมโยงกันภายใต้แบรนด์ 'ฮิมาวาริ' เราได้พูดคุยเรื่องนี้กันมาตั้งแต่ปีที่แล้ว และเราเชื่อว่าจะสามารถปลูกพืชผลได้โดยใช้ปุ๋ยดอกทานตะวันคุณภาพสูงที่ปลอดภัย
- นายกเทศมนตรีซาซากิ:“พวกเรายังรู้สึกขอบคุณโรงเรียน Dairy Farm School สำหรับความปรารถนาที่จะแก้ไขปัญหาความเสียหายที่เกิดจากนกและสัตว์ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับความสำคัญของชีวิต”
▶︎มหาวิทยาลัยราคุโนะ กักคุเอ็น: การใช้ความรู้เฉพาะทาง
- ศาสตราจารย์อาเบะ:เรามีความสัมพันธ์อันยาวนานกับพวกเขาในเรื่องน้ำมันดอกทานตะวันคุณภาพสูง และมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาของเราทุกปี ความร่วมมือครั้งล่าสุดนี้จะเป็นข้อตกลงที่ไม่เพียงแต่เกิดขึ้นระหว่างห้องปฏิบัติการของเราเท่านั้น แต่จะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยทั้งหมดด้วย
- ประธานาธิบดีอิวาโนะ:มหาวิทยาลัยของเราตั้งอยู่บนแนวคิด ‘เกษตร อาหาร สิ่งแวดล้อม และชีวิต’ ยกตัวอย่างเช่น ในสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม เรามีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่วิเคราะห์และวิเคราะห์ภาพจากโดรน การถ่ายภาพพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่จากมุมสูงช่วยสนับสนุนงานเกษตรกรรมที่มีประสิทธิภาพได้ เมื่อพูดถึงความเสียหายที่เกิดจากนกและสัตว์ป่า ประเด็นสำคัญคือการอยู่ร่วมกับมนุษย์อย่างไร โดยพิจารณาจากประสบการณ์การทำงานในภูมิภาคอื่นๆ เราจะพิจารณาแนวทางรับมือกับปัญหานี้กับเมืองโฮคุริวในอนาคต
2. ความร่วมมือเฉพาะระหว่างนักศึกษาและเมือง
- ประธานาธิบดีอิวาโนะ:ที่มหาวิทยาลัยของเรา เมื่อนักศึกษาเข้าสู่วัยเกษียณ พวกเขาจะเข้าร่วมห้องปฏิบัติการวิจัย ลงพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นตามหัวข้อที่กำหนด และใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหา ในฐานะมหาวิทยาลัย เราต้องการพัฒนาวิธีการแบบอินเทอร์แอคทีฟที่ชี้ให้เห็นปัญหาผ่านการพูดคุยกับคนในท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอแนวคิดของตนเอง
- ศาสตราจารย์อาเบะ:เราเห็นว่าการขาดแคลนผลิตภัณฑ์เฉพาะทางในโฮคุริวเป็นปัญหาสำคัญต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดของเรายังกล่าวอีกว่าพวกเขาต้องการค้นหาทรัพยากรที่ซ่อนอยู่ในโฮคุริวและนำทรัพยากรเหล่านั้นมาใช้เพื่อฟื้นฟูภูมิภาค เราหวังว่าการตลาดโดยใช้น้ำมันดอกทานตะวันเป็นจุดเริ่มต้นจะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะทางและการฟื้นฟูภูมิภาค
- นายกเทศมนตรีซาซากิ:ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและชาวเมืองได้จุดประกายให้เกิดการสนทนา และชาวเมืองจำนวนมากได้รู้จักเมืองนี้มากขึ้น เมืองนี้พัฒนาไปอย่างมากในช่วงสามปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน เราอยู่ในช่วงแรก และตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่สอง ด้วยจำนวนประชากรในเมืองที่ลดลงต่ำกว่า 1,600 คน การรักษาจำนวนประชากรที่มาเยือนและประชากรที่เกี่ยวข้องจึงเป็นประเด็นสำคัญ เมื่อนักศึกษาที่เคยมาเยือนครั้งหนึ่งกลับมาอีกครั้งหรือครั้งที่สาม พวกเขาก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ "ประชากรที่เกี่ยวข้อง" เมื่อเรายื่นขอทุนฟื้นฟูภูมิภาค เราได้ตั้งเป้าหมาย KPI (เป้าหมายเชิงตัวเลข) ไว้ที่ "ประชากรที่เกี่ยวข้อง 1,600 คน" เราจะทำงานอย่างหนักเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ดังนั้นเราขอความร่วมมือจากทุกท่านอย่างต่อเนื่อง
ภาพถ่ายที่ระลึกที่ Himawari no Sato
หลังจากพิธีลงนาม เราได้เดินทางไปยังหมู่บ้านดอกทานตะวัน ซึ่งดอกทานตะวันกำลังบานสะพรั่ง และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก รอยยิ้มของทุกคนดูเหมือนจะเป็นสัญลักษณ์แห่งอนาคตอันสดใสของเมืองโฮคุริว
ด้วยความรัก ความกตัญญู และคำอธิษฐานอันไร้ขอบเขต เราหวังว่าการเชื่อมต่อที่ยอดเยี่ยมระหว่างมหาวิทยาลัย Rakuno Gakuen และเมือง Hokuryu จะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายเปล่งประกายเจิดจรัสยิ่งขึ้นในสีสันแห่งสายรุ้ง และพัฒนาต่อไป